指導医からのメッセージ
内科専攻医|沓名健雄 医師
内科専門研修 / プログラム統括責任者

◆6カ月~最長2年!
自由に期間を設定できる内科全科ローテ
404床の中規模病院でありながら、血液内科や腎臓内科などの専門的な領域も含む内科9科全科をローテーションし、幅広い経験を積めることが当院内科プログラムの最大の特長です。横断的診療領域である膠原病や感染症のプロフェッショナルが集まる「総合内科」では、たくさんの鑑別が必要な症例や複合疾患の症例を診ます。それは急性期・慢性期を問わず、現在の医療に大きく必要とされる、いわゆる老年内科の領域にまで及びます。
内科専門研修は、この総合内科を含む全ての内科を研修することによって内科医としての基礎を整え、その後のジェネラリストもしくはスペシャリストへ向けての下地を確実に醸成します。全体として診療科の垣根が低く、いろいろな科の専門医に相談しやすい環境も、当院の魅力です。
(呼吸器内科 主任部長)

内科専攻医|沓名健雄 医師
内科専門研修 / プログラム統括責任者
◆6カ月~最長2年!自由に期間を設定できる内科全科ローテ
404床の中規模病院でありながら、血液内科や腎臓内科などの専門的な領域も含む内科9科全科をローテーションし、幅広い経験を積めることが当院内科プログラムの最大の特長です。横断的診療領域である膠原病や感染症のプロフェッショナルが集まる「総合内科」では、たくさんの鑑別が必要な症例や複合疾患の症例を診ます。それは急性期・慢性期を問わず、現在の医療に大きく必要とされる、いわゆる老年内科の領域にまで及びます。
内科専門研修は、この総合内科を含む全ての内科を研修することによって内科医としての基礎を整え、その後のジェネラリストもしくはスペシャリストへ向けての下地を確実に醸成します。全体として診療科の垣根が低く、いろいろな科の専門医に相談しやすい環境も、当院の魅力です。
(呼吸器内科 主任部長)
内科指導医|志水英明 医師
内科専門研修 / 管理委員長

◆ジェネラルマインドを持った
スペシャリストになる!
専攻医が希望するキャリアに沿って、多様な経験を積むことができるのが当院の内科です。
1年目のローテート研修は、期間をフレキシブルに設定することができます。また週1回サブスペシャルティ診療科の業務を行うことができるため幅広く診つつも専門領域について並行して学ぶことができます。各専門診療科はいずれも教育認定施設で、専門医を目指しやすい環境が整っています。多くの有力研修病院と連携を組んでおり、もっと極めたい・深めたい分野を学ぶための往き来が盛んです。
当法人の方針は高度急性期と地域包括ケアの拡充です。迫りくる超高齢化社会を目の当たりにしながら、全人的な医療というマインドも培われていきます。
専攻医の病歴要約を全内科でレビューしあう会や、毎週のMKSAP勉強会、著名な院外講師を招いての勉強会など学び・教える機会も多彩です。ぜひ大同病院の内科を見に来てほしいと思っています。
(大同病院副院長/腎臓内科部長)
内科指導医|志水英明 医師
内科専門研修 / 管理委員長
◆ジェネラルマインドを持ったスペシャリストになる!
専攻医が希望するキャリアに沿って、多様な経験を積むことができるのが当院の内科です。
1年目のローテート研修は、期間をフレキシブルに設定することができます。また週1回サブスペシャルティ診療科の業務を行うことができるため幅広く診つつも専門領域について並行して学ぶことができます。各専門診療科はいずれも教育認定施設で、専門医を目指しやすい環境が整っています。多くの有力研修病院と連携を組んでおり、もっと極めたい・深めたい分野を学ぶための往き来が盛んです。
当法人の方針は高度急性期と地域包括ケアの拡充です。迫りくる超高齢化社会を目の当たりにしながら、全人的な医療というマインドも培われていきます。
専攻医の病歴要約を全内科でレビューしあう会や、毎週のMKSAP勉強会、著名な院外講師を招いての勉強会など学び・教える機会も多彩です。ぜひ大同病院の内科を見に来てほしいと思っています。
(大同病院副院長/腎臓内科部長)
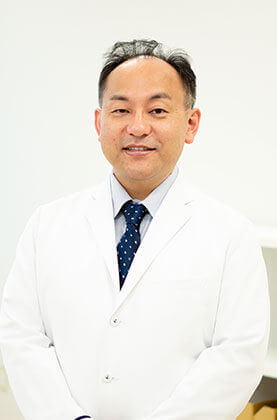
小児科専攻医|浅井雅美 医師
小児科専門研修 / プログラム統括責任者

◆小児科医への第一歩を踏み出すなら大同で
当院の小児科には、新生児から中学生くらいまで、プライマリから専門的に診るべき疾患例まで、あらゆる小児医療の症例が集まってきます。救急は24時間365日常に受け入れていて、2次救急はもとより最近では2.5次から一部3次救急にかかるような重症例も増加しており、さまざまな疾病治療にかかわることができます。目の前にいる患者さんを、自ら考えて診ていかなければならない機会が山ほどあれば、勉強せざるを得ないですし、学んだことの定着率も格段に上がります。そんな専攻医1人に対して、2人の上級医(小児科専門医)がチームになって、治療方針の客観的な評価や振り返り、困ったときの相談などにいつでも乗れる指導体制を築いています。個々の良さを引き出し、どこに出しても恥ずかしくない「一人前の小児科医」を育てることをモットーとしています。
育児中の若手医師も多いですが、託児所や病児保育施設、また勤務制度等が整っていることもあり、お互いが助け合って小児医療を支えているところも当院の特徴ですね。
(宏潤会理事/副院長/小児科部長)

小児科専攻医|浅井雅美 医師
小児科専門研修 / プログラム統括責任者
◆小児科医への第一歩を踏み出すなら大同で
当院の小児科には、新生児から中学生くらいまで、プライマリから専門的に診るべき疾患例まで、あらゆる小児医療の症例が集まってきます。救急は24時間365日常に受け入れていて、2次救急はもとより最近では2.5次から一部3次救急にかかるような重症例も増加しており、さまざまな疾病治療にかかわることができます。目の前にいる患者さんを、自ら考えて診ていかなければならない機会が山ほどあれば、勉強せざるを得ないですし、学んだことの定着率も格段に上がります。そんな専攻医1人に対して、2人の上級医(小児科専門医)がチームになって、治療方針の客観的な評価や振り返り、困ったときの相談などにいつでも乗れる指導体制を築いています。個々の良さを引き出し、どこに出しても恥ずかしくない「一人前の小児科医」を育てることをモットーとしています。
育児中の若手医師も多いですが、託児所や病児保育施設、また勤務制度等が整っていることもあり、お互いが助け合って小児医療を支えているところも当院の特徴ですね。
(宏潤会理事/副院長/小児科部長)
小児科指導医|早川 梢 医師
上級医

◆経験を重ねて体得することが一番。
だから大同病院
小児科は、ひとりの患者さんでもその成長とともに“患者像”がどんどん変わっていきます。ゆえに診療計画を立てる上で、長期的な見通しが大事になってくることも多いのですが、その児が大きくなってからどうなるか、長い目で捉えた方向性を考えることはなかなか困難です。わたしも専攻医時代には、上級医の先生たちのようにうまく先を見通せず、よく悩みました。しかし年数を経るにつれ、実際に成長する児とともに、徐々に身についていくのを感じています。
こどものことなら何でも診るのが小児科、なかでも急性期から在宅医療まで広範な領域に関われるのが大同病院です。市中病院として多様かつ豊富な症例が集まってくる。私はサブスペシャルティを決めることにも苦労するほど、その魅力を十二分に味わい、幅広い症例とその経過から多くのことを学んでいます。専攻医のみなさんに年齢的にも近い私は、ちょっとしたことでも気軽に相談してもらえる立場。自らが悩んできたことも踏まえ、先生たちをサポートしています。
(小児科医師)
小児科指導医|早川 梢 医師
上級医
◆経験を重ねて体得することが一番。だから大同病院
小児科は、ひとりの患者さんでもその成長とともに“患者像”がどんどん変わっていきます。ゆえに診療計画を立てる上で、長期的な見通しが大事になってくることも多いのですが、その児が大きくなってからどうなるか、長い目で捉えた方向性を考えることはなかなか困難です。わたしも専攻医時代には、上級医の先生たちのようにうまく先を見通せず、よく悩みました。しかし年数を経るにつれ、実際に成長する児とともに、徐々に身についていくのを感じています。
こどものことなら何でも診るのが小児科、なかでも急性期から在宅医療まで広範な領域に関われるのが大同病院です。市中病院として多様かつ豊富な症例が集まってくる。私はサブスペシャルティを決めることにも苦労するほど、その魅力を十二分に味わい、幅広い症例とその経過から多くのことを学んでいます。専攻医のみなさんに年齢的にも近い私は、ちょっとしたことでも気軽に相談してもらえる立場。自らが悩んできたことも踏まえ、先生たちをサポートしています。
(小児科医師)

経験する医療の幅広さは、当院ならではのもの

大同病院は「高度急性期医療」と「地域最高の包括ケアシステムを構築する」という2つの軸を大切にしています。
治すだけでなく、患者さんが治った後、どのように元の生活に戻れるかまで、地域の中のさまざまなステークホルダーと一緒に考え、そして地域共生社会の構築に貢献していく、というのが当院のめざす姿です。
その目標への道を、ぜひ研修医の皆さんも一緒に歩いてください。
大同病院 病院長・プログラムディレクター
野々垣浩二

経験する医療の幅広さは、当院ならではのもの
大同病院は「高度急性期医療」と「地域最高の包括ケアシステムを構築する」という2つの軸を大切にしています。
治すだけでなく、患者さんが治った後、どのように元の生活に戻れるかまで、地域の中のさまざまなステークホルダーと一緒に考え、そして地域共生社会の構築に貢献していく、というのが当院のめざす姿です。
その目標への道を、ぜひ研修医の皆さんも一緒に歩いてください。
大同病院 病院長・プログラムディレクター 野々垣浩二